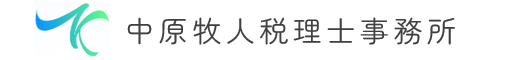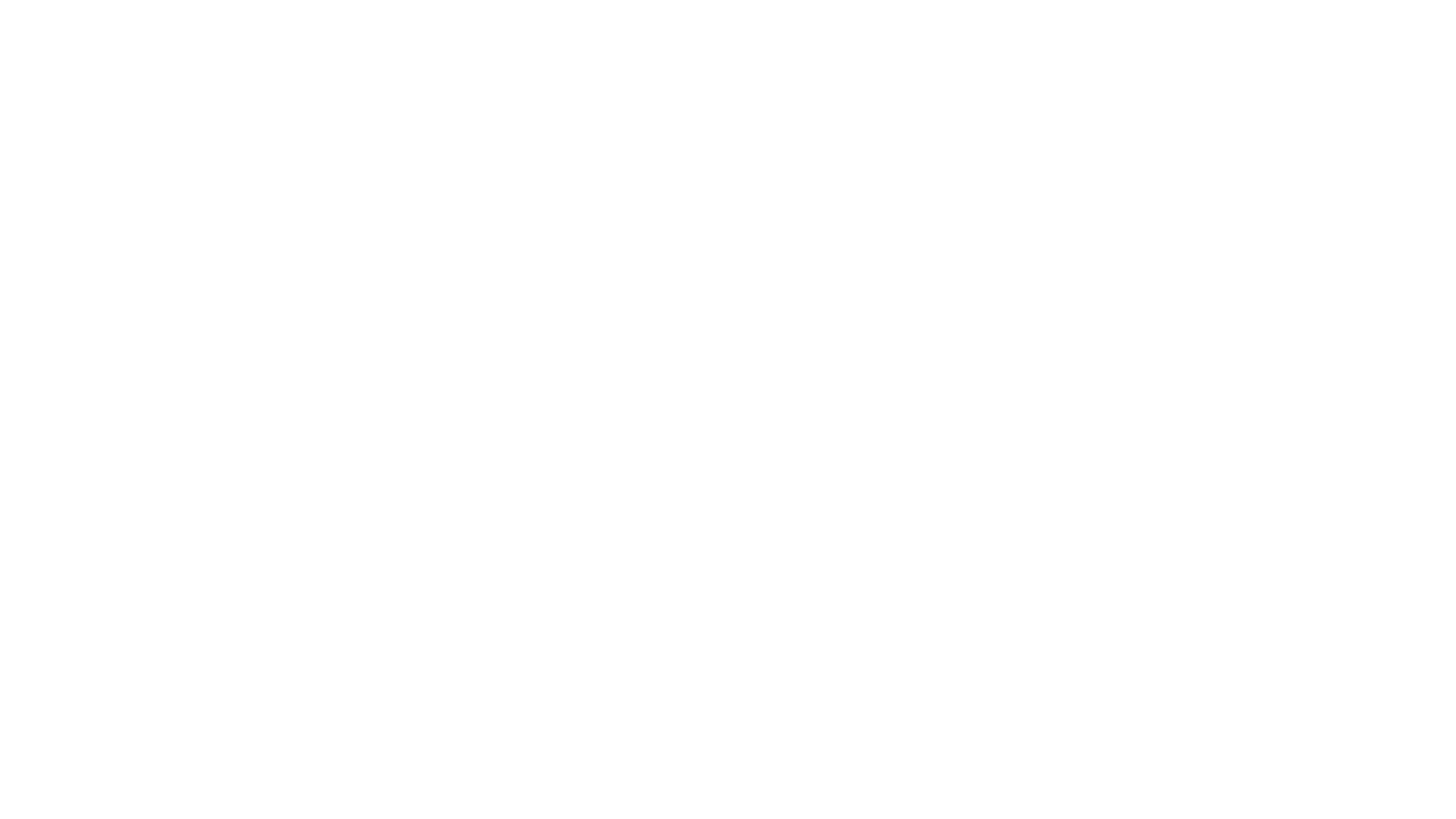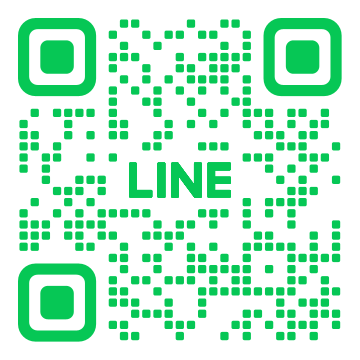配偶者控除(軽減)は期限後申告でも使えるの?未分割の期限内申告だけではありません!
2019年4月18日

相続税を計算するうえで、配偶者には強烈な優遇制度があります。
申告期限(亡くなってから10か月以内)を過ぎると使えないと思われがちですが、間に合わなくても使える可能性があります。
配偶者控除(税額軽減)とは?
相続税において、配偶者はかなり優遇されています。
- ひとりになってしまった生活を保障する
- 亡くなられた方の財産形成に貢献している
といった理由があるため、できるだけ相続税をとらず、お金が多く残るようになっているのです。
具体的には、配偶者が取得する財産が、
- 1億6000万円
- 法律で決められた取り分
までなら、配偶者の相続税は0円になります。
法律で決められた取り分(法定相続分)は、相続人の構成によってちがい、
- 配偶者と子供→1/2
- 配偶者と両親→2/3
- 配偶者と兄弟→3/4
のように、配偶者と相続人の関係が遠くなるだけ、配偶者の取り分が増えるようになっています。
(実際に遺産をわけるうえで従う必要はありません)
配偶者控除(軽減)を使うためには遺産分割が必要
配偶者控除(軽減)を使うためには、配偶者がどの財産を相続するか決めないといけません。
つまり、申告期限までに遺産のわけ方が決まらない場合、期限内の申告では使えないのです。
しかし、「3年以内にわける予定です」という書類(分割見込書)をつけて申告し、わけ方が決まったら「払いすぎた相続税をかえして」という手続きをすれば問題ありません。
では、申告期限までに、
- 遺産のわけ方が決まらない
- 申告書の提出も間に合わない
となった場合、どうなるのでしょうか?
遺産分割の方法は3種類?不動産が多いなら換価分割も検討しましょう!
配偶者控除(軽減)は期限後申告でも適用可
結論としては、期限後の申告になっても、「申告期限から3年以内」なら使うことができます。
なぜなら、そもそもの目的が「配偶者の保護」であり、期限を過ぎても「配偶者が財産をもらう事実はかわらない」からです。
期限後に申告する場合、すでにわけ方は決まっているので「分割見込書」をつける必要はありません。
ちなみに、同居している家族などを保護する制度(小規模宅地等の特例)でも同じように、期限後の申告で使うことができます。
(農地・株の納税猶予は期限内じゃないとだめです)
まとめ
配偶者控除(軽減)について書きました。
期限後の申告になると、延滞税といった罰金がかかってしまいます。
できることなら、申告期限までに分割見込書をつけて提出するようにしましょう。
■娘日記
娘とふたりで実家デートに。
両親の甘やかしっぷりはわたしといい勝負です。
関連記事
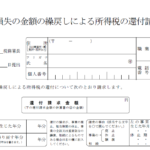
個人事業の損失は繰越しだけではない!前年に戻って税金をかえしてもらえます!
こんにちは。ガリガリ税理士の中原(@makito_tax)です。 ...
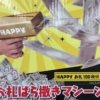
保険金をそのまま役員の死亡退職金として支払うと問題あり?法人保険のメリットとは?
保険に入る「本来の目的」を忘れないように。 保険本来の目的は万が一 ...

役員報酬の変更は4ヶ月目でもOK!定期同額給与の3ヶ月の意味とは?
役員報酬でまちがえやすい、「3ヶ月以内に変更しなさい」というルール。 じつは、3 ...
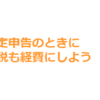
【インボイス制度】確定申告で税金(消費税)が経費になる?フリーランス・個人事業主は忘れずに計算しよう!
インボイスに登録した方の中には、2024年にはじめて消費税の申告をする方がいます ...

資本的支出とは?わかりやすく修繕費とのちがいを説明します!
こんにちは。ガリガリ税理士の中原(@makito_tax)です。 ...
中原牧人(まきと)

1987年、島根生まれ岡山育ち。合同会社MIOコンサルティング 代表社員|中原牧人税理士事務所 代表税理士|一般社団法人はれとこ 監事
web3(仮想通貨・NFT・DAO)、AIサービス、IT効率化に強い税理士。岡山県を中心に全国のひとり社長やフリーランスをサポートしている。
ゲームとマンガが大好きなJanner。
10歳の娘を溺愛している。
メディア出演 / セミナー実績
2017/12/12
津山市役所 青色申告説明会
2018/12/11
津山税務署 決算申告説明会
2020/3/4
浅口商工会 確定申告相談会
2021/1/10
岡山県青年司法書士協議会 相続相談会
2021/3/21
岡山ブログカレッジ 税理士に聞くブロガーの確定申告
2021/8/12
FMくらしき おまかせラジオ
2021/10/24
高梁川流域ライター塾2021 ライターに必要な税金の知識
2021/11/23
岡山県立図書館 相続相談会
2022/10/2
高梁川流域ライター塾2022 ライターに必要な税金の知識
2022/11/30
田舎のひとり税理士でも売上ゼロから2年で食べていけるようになるぞセミナー
2023/10/8
高梁川流域ライター塾2023 ライターに必要な税金の知識
2024/9/8
高梁川流域ライター塾2024 ライターに必要な税金の知識
カテゴリー
YouTube【平日18時更新】
-
ホーム -
メニュー -
サイドバー